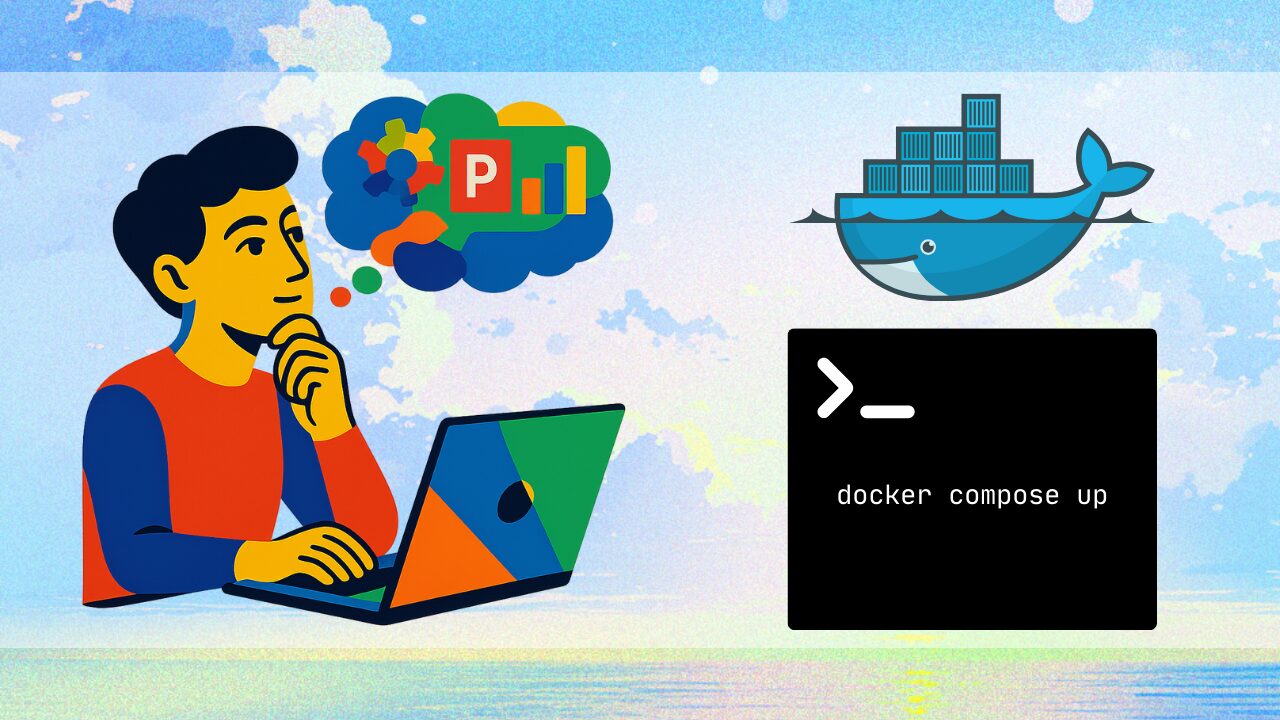Docker Compose を使って開発環境を立ち上げるとき、多くの方が最初に使うのが docker compose up コマンドです。シンプルに実行するだけでもコンテナは起動しますが、実際の開発現場では「バックグラウンドで動かしたい」「特定のサービスだけ立ち上げたい」「キャッシュを無視してビルドし直したい」といったシーンが頻繁にあります。ところが、いざオプションを付けてみようとすると種類が多く、どの場面でどのオプションを選べばいいのか迷ってしまう方も少なくありません。
また、「docker compose up が終わらない」「キャッシュが残って正しく動かない」「複数の docker-compose.yml を切り替えたい」といったトラブルに直面することもあります。これらはオプションの理解が浅いと解決に時間がかかり、開発効率を大きく下げてしまう原因にもなります。
そこでこの記事では、現場でよく使われる基本的なオプションから、知っていると便利な実践テクニック、さらにはトラブルシューティングや環境ごとの使い分けまで体系的に整理しました。Docker Compose を日常的に使うエンジニアが、必要な情報を一つの記事でキャッチアップできる内容になっています。
「docker compose up オプション」を正しく理解すれば、開発効率は大幅にアップし、チーム内でも一歩リードできる存在になれるはずです。それでは、基本から応用まで順を追って見ていきましょう。
Docker Composeとdocker compose upの概要
Docker Composeは、複数のコンテナで構成されるアプリケーションを定義し、実行するためのツールです。YAMLファイルを使用して、アプリケーションのサービスを全て設定できるため、コマンドを一つ実行するだけで、定義したすべてのコンテナをまとめて起動、停止、再構築、管理できます。これにより、個々のコンテナを手動で管理する手間が省け、開発やテスト、本番環境の構築が大幅に効率化されます。

Docker Composeの主な機能とメリット
Docker Composeが提供する主な機能は、単一のファイル(通常はdocker-compose.yml)に複数のコンテナサービスを記述できる点です。このファイルには、各サービスのDockerイメージ、ポート、ボリューム、ネットワーク、環境変数、そして他のサービスへの依存関係などを定義します。
このツールの最大のメリットは、以下のとおりです。
環境構築の簡素化
複雑なアプリケーション(例:Webサーバー、データベース、キャッシュサーバーなど)も、一つの設定ファイルで定義し、一つのコマンドで簡単に起動できます。これにより、チームメンバー間や異なる環境間での設定のばらつきを防ぎ、誰でも同じ開発環境を素早く構築できるようになります。
開発効率の向上
docker compose upコマンドを使えば、サービスの再構築や再起動を簡単に行えます。特に開発時には、--buildオプションと組み合わせることで、ソースコードの変更をコンテナに素早く反映させられます。
コンテナ間の連携
docker-compose.ymlファイル内でサービス間の依存関係(depends_on)やネットワークを簡単に定義できるため、サービス同士がスムーズに連携して動作するようになります。
DockerとDocker Composeの関係
DockerとDocker Composeは、密接に関連していますが役割が異なります。
Docker
個々のコンテナを作成、管理するツールです。Dockerfileを使って単一のコンテナイメージをビルドし、docker runコマンドでそれを実行します。
Docker Compose
複数のDockerコンテナをまとめて管理するためのオーケストレーションツールです。複数のコンテナを扱うアプリケーションでは、Docker単体で管理するよりもDocker Composeを使う方がはるかに効率的です。
単一のコンテナで動作するアプリケーションであればDockerだけで十分ですが、Webアプリケーションのバックエンド、データベース、フロントエンドをそれぞれ別のコンテナとして管理するような複雑な構成では、Docker Composeが不可欠なツールとなります。
docker compose up コマンドの概要
docker compose up は、Docker Compose の主要なコマンドの一つで、docker-compose.yml ファイルに定義されたすべてのサービスを起動するために使われます。このコマンドを実行すると、Docker Compose は以下の作業を自動的に行ってくれます。
サービスの定義を読み込む
まず、カレントディレクトリにある docker-compose.yml ファイルを読み込み、アプリケーションを構成するサービスやネットワーク、ボリュームなどの定義を確認します。
イメージの構築(必要な場合)
もし docker-compose.yml に build 命令が含まれていて、まだ Docker イメージが構築されていない場合、自動的にイメージを構築します。このとき、Dockerfile の内容に基づいてコンテナの実行環境が準備されます。
コンテナの作成と起動
定義されたサービスごとにコンテナを作成し、起動します。コンテナは指定されたポートや環境変数、ボリュームなどの設定に従って実行されます。
このコマンドの大きなメリットは、複数のコンテナをたった一つのコマンドでまとめて起動できる点です。これにより、個々のコンテナを手動で管理する手間が省け、開発環境やテスト環境の構築が非常に効率的になります。
docker compose upの基本オプション一覧と使い方
docker compose upコマンドは、単体で実行することも可能ですが、様々なオプションを組み合わせることで、開発効率を大幅に向上させることができます。このセクションでは、docker compose up オプションの中でも特に重要なものから、実践的な活用方法まで詳しく解説します。
まずはこれだけ!よく使う必須オプション5選
1. docker compose up -d:バックグラウンド実行(デタッチモード)
なぜバックグラウンドで起動したいのか?
d(-detach)オプションは、コンテナをバックグラウンドで実行するためのオプションです。このオプションを使用しない場合、ターミナルがコンテナのログ出力で占有されてしまい、他の作業ができなくなってしまいます。特に複数のサービスを起動する場合、各サービスのログが混在して読みにくくなるため、デタッチモードでの起動は開発現場では必須と言えます。
コード例:
# バックグラウンドでサービスを起動
docker compose up -d
# 起動後にログを確認したい場合
docker compose logs
# 特定のサービスのログのみを確認
docker compose logs web
# リアルタイムでログを追跡
docker compose logs -f
docker-compose.yml例:
version: '3.8'
services:
web:
build: .
ports:
- "3000:3000"
db:
image: postgres:13
environment:
POSTGRES_PASSWORD: password
2. docker compose up --build:イメージの再ビルド
-buildが必要なのはどんな時か?
-buildオプションは、docker compose up実行前にDockerイメージを再ビルドするオプションです。以下のような場合に特に重要です:
Dockerfileやビルドコンテキストに変更を加えた場合- ソースコードを更新してコンテナに反映させたい場合
- 依存関係(
package.json、requirements.txtなど)を更新した場合
なお、docker compose buildコマンドとの違いは、--buildオプションはビルド後に自動的にコンテナを起動する点です。docker compose buildは単純にイメージをビルドするのみで、起動は別途docker compose upが必要です。
コード例:
# イメージを再ビルドしてからサービスを起動
docker compose up --build
# バックグラウンドで再ビルド&起動
docker compose up -d --build
# 特定のサービスのみ再ビルド&起動
docker compose up --build web
3. docker compose up --force-recreate:コンテナの強制再作成
なぜ再作成が必要なのか?
-force-recreateオプションは、既存のコンテナを削除してから新しいコンテナを作成するオプションです。以下のような場合に効果的です:
docker-compose.ymlの設定(環境変数、ボリューム設定など)を変更した場合- コンテナの内部状態をクリアにリセットしたい場合
- 原因不明の問題が発生した際のトラブルシューティング
コード例:
# 全コンテナを強制的に再作成
docker compose up --force-recreate
# バックグラウンドで強制再作成
docker compose up -d --force-recreate
# 特定のサービスのみ強制再作成
docker compose up --force-recreate web
4. docker compose up --no-deps:依存関係を無視して起動
特定のサービスだけを起動したい場合に便利
-no-depsオプションは、docker-compose.ymlで定義されたdepends_onを無視して、指定されたサービスのみを起動するオプションです。開発中に特定のサービスだけをテストしたい場合や、依存関係のあるサービスがすでに起動している場合に便利です。
コード例:
# webサービスのみを起動(dbサービスは起動しない)
docker compose up --no-deps web
# バックグラウンドで依存関係を無視して起動
docker compose up -d --no-deps api
docker-compose.yml例:
version: '3.8'
services:
web:
build: .
depends_on:
- db # 通常はdbサービスも起動されるが、--no-depsで無視される
ports:
- "3000:3000"
db:
image: postgres:13
environment:
POSTGRES_PASSWORD: password
5. docker compose up [サービス名]:特定のサービスを起動
複数のサービスがある場合に特定のサービスだけを起動
サービス名を指定することで、docker-compose.ymlに定義された複数のサービスの中から、必要なサービスのみを選択的に起動できます。開発中に全てのサービスが不要な場合や、リソースを節約したい場合に有効です。
コード例:
# データベースサービスのみを起動
docker compose up mysql
# 複数のサービスを指定して起動
docker compose up web redis
# バックグラウンドで特定のサービスを起動
docker compose up -d api db
# 依存関係も含めて特定のサービスを起動(デフォルト動作)
docker compose up web # depends_onで指定されたサービスも自動起動
docker-compose.yml例:
version: '3.8'
services:
web:
build: .
depends_on:
- db
- redis
ports:
- "3000:3000"
api:
build: ./api
ports:
- "8000:8000"
db:
image: mysql:8.0
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
redis:
image: redis:7-alpine
目的別!開発現場で役立つ実践オプション
-no-recreate:既存コンテナを再作成しない
既存のコンテナが存在する場合、それを再利用してサービスを起動します。開発中にデータベースの内容を保持したまま他のサービスだけを再起動したい場合に便利です。
開発シーン例: データベースに蓄積したテストデータを失いたくない場合
docker compose up --no-recreate
-quiet-pull:イメージ取得時のログを抑制
Dockerイメージをpullする際の進捗ログを非表示にします。CI/CDパイプラインでログを見やすくしたい場合や、ネットワーク帯域が狭い環境での実行時に有効です。
開発シーン例: CI/CDでの自動デプロイ時にログをスッキリさせたい場合
docker compose up -d --quiet-pull
-remove-orphans:docker-compose.ymlに定義されていない不要なコンテナを削除
現在のdocker-compose.ymlに定義されていない古いコンテナを自動的に削除します。プロジェクトの進行に伴ってサービス構成が変わった際に、環境をクリーンに保つことができます。
開発シーン例: サービス構成を変更して不要になったコンテナが残っている場合
docker compose up -d --remove-orphans
-abort-on-container-exit:いずれかのコンテナが停止したら、全てを停止
いずれか一つのコンテナが停止した時点で、全てのサービスを停止します。相互に依存関係の強いサービス群を管理する際や、一つのサービスの異常終了を早期に検知したい場合に有効です。
開発シーン例: マイクロサービス間の依存関係が強く、一つでも停止したら全体を停止させたい場合
docker compose up --abort-on-container-exit
-renew-anon-volumes:匿名ボリュームを新規作成
既存の匿名ボリュームを削除して新しいボリュームを作成します。データベースの初期化やキャッシュのクリアが必要な場合に使用します。
開発シーン例: データベースの初期データをリセットしてテストを行いたい場合
docker compose up --renew-anon-volumes
デバッグとトラブルシューティングに役立つコマンドオプション
開発中に問題が発生した際、以下のオプションを組み合わせることで効率的にトラブルシューティングを行うことができます:
基本的なトラブルシューティングフロー
-force-recreateでコンテナを完全に再作成-buildでイメージの再ビルドを強制-remove-orphansで不要なコンテナを削除dでバックグラウンド実行し、logsコマンドでログ確認
# 完全クリーンな状態で再起動(トラブルシューティングの基本)
docker compose up -d --build --force-recreate --remove-orphans
# 起動後、ログでエラーを確認
docker compose logs
# 特定のサービスに問題がある場合
docker compose logs web
docker compose logs -f db # リアルタイム監視
よく使用される組み合わせパターン
# 開発中の標準的な再起動
docker compose up -d --build
# トラブル時の完全リセット
docker compose down && docker compose up -d --build --force-recreate --remove-orphans
# 特定のサービスのみ検証
docker compose up --no-deps --build api
これらのdocker compose up オプションをマスターすることで、開発効率が大幅に向上し、トラブル発生時の対応もスムーズになります。次のセクションでは、これらのオプションをより実践的に活用するテクニックについて詳しく解説していきます。
実践で使えるdocker compose upオプションテクニック
基本的なdocker compose up オプションをマスターしたら、次は実際の開発現場でより効率的に作業するための実践的なテクニックを身につけましょう。このセクションでは、複数の設定ファイルを使い分けたり、特定のサービスのみを起動したりする高度な活用方法について詳しく解説します。

fオプションで複数のdocker-compose.ymlファイルを指定する方法
開発環境と本番環境の設定を分ける実践的なアプローチ
実際の開発現場では、開発環境と本番環境で異なる設定が必要になることがほとんどです。-f(--file)オプションを活用することで、環境ごとに適切な設定を適用できます。
典型的なファイル構成:
project/
├── docker-compose.yml # 基本設定
├── docker-compose.dev.yml # 開発環境用設定
├── docker-compose.prod.yml # 本番環境用設定
└── docker-compose.override.yml # ローカル開発用設定(自動読み込み)
基本的な使い方とコード例
docker-compose.yml(基本設定):
version: '3.8'
services:
web:
build: .
environment:
- NODE_ENV=production
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_DB=myapp
docker-compose.dev.yml(開発環境用):
version: '3.8'
services:
web:
ports:
- "3000:3000"
environment:
- NODE_ENV=development
- DEBUG=true
volumes:
- .:/app # ホットリロード用
db:
ports:
- "5432:5432" # デバッグ用にポート公開
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=dev_password
docker-compose.prod.yml(本番環境用):
version: '3.8'
services:
web:
environment:
- NODE_ENV=production
deploy:
replicas: 3
db:
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD} # 環境変数から取得
volumes:
- db_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
db_data:
実践的なコマンド例
# 開発環境で起動
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d
# 本番環境で起動
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d
# 複数ファイル指定でビルドも実行
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build
# 特定のサービスのみを複数設定ファイルで起動
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d web
docker-compose.override.ymlの自動読み込み機能
Docker Composeは、docker-compose.ymlと同じディレクトリにdocker-compose.override.ymlがある場合、自動的に両方のファイルを読み込みます。個人の開発環境設定に最適です。
docker-compose.override.yml例:
version: '3.8'
services:
web:
ports:
- "3001:3000" # ポート番号を個人設定に変更
environment:
- DEBUG_LEVEL=verbose
# override.ymlがあれば自動的に適用される
docker compose up -d
# override.ymlを無視したい場合
docker compose -f docker-compose.yml up -d
特定サービスだけを起動する:サービス名指定のベストプラクティス
depends_onとの関係を理解する
docker compose upでサービス名を指定する際、depends_onで定義された依存関係が重要な役割を果たします。
docker-compose.yml例:
version: '3.8'
services:
web:
build: .
depends_on:
- db
- redis
ports:
- "3000:3000"
api:
build: ./api
depends_on:
- db
ports:
- "8000:8000"
worker:
build: ./worker
depends_on:
- db
- redis
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=password
redis:
image: redis:7-alpine
実践的なサービス起動パターン
# webサービスを起動(depends_onによりdbとredisも自動起動)
docker compose up -d web
# apiサービスのみを起動(dbも自動起動)
docker compose up -d api
# 複数のサービスを明示的に指定
docker compose up -d api worker
# 依存関係を無視してwebサービスのみ起動
docker compose up -d --no-deps web
# データベースとキャッシュだけを起動(バックエンドサービスは起動しない)
docker compose up -d db redis
開発フェーズ別の活用例
フロントエンド開発時:
# フロントエンド開発に必要な最小構成
docker compose up -d db redis
# 外部APIサーバーを使用する場合
docker compose up -d --no-deps web
API開発時:
# API開発に集中したい場合
docker compose up -d db redis api
データベース設計・検証時:
# データベースのみ起動してSQLクライアントで接続
docker compose up -d db
-remove-orphans・-abort-on-container-exitなど便利な制御オプションまとめ
-remove-orphansの詳細活用法
なぜ--remove-orphansが便利なのか?
プロジェクトの進行に伴い、docker-compose.ymlからサービスを削除したり、サービス名を変更したりすることがあります。この際、古いコンテナが残り続けてしまい、以下のような問題が発生します:
- 不要なリソースの消費
- ポート競合の発生
- ログの混在による障害調査の困難化
実践的な使用例:
# サービス構成を変更した後のクリーンアップ
docker compose up -d --remove-orphans
# 完全なクリーンアップを行いたい場合
docker compose down --remove-orphans
docker compose up -d --build --remove-orphans
具体的なシナリオ例:
元のdocker-compose.yml:
services:
web:
build: .
old-service: # 後で削除予定のサービス
image: nginx
db:
image: postgres:13
更新後のdocker-compose.yml:
services:
web:
build: .
new-service: # old-serviceを置き換え
image: nginx
db:
image: postgres:13
# old-serviceコンテナが自動的に削除される
docker compose up -d --remove-orphans
-abort-on-container-exitの実践的活用
どんな場面で役立つか?
- 一回限りのタスク実行:データ移行、テスト実行など
- 相互依存の強いサービス群:一つでも停止したら全体を停止したい場合
- CI/CDパイプライン:テスト完了後に全てのサービスを停止したい場合
コード例:
# テスト実行用のdocker-compose.test.yml
version: '3.8'
services:
test-runner:
build: .
command: npm test
depends_on:
- db
- redis
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=test_password
redis:
image: redis:7-alpine
# テスト完了後、自動的に全サービスが停止
docker compose -f docker-compose.test.yml up --abort-on-container-exit
# ログを確認しながら実行(非デタッチモード)
docker compose -f docker-compose.test.yml up --abort-on-container-exit
複数オプションの効果的な組み合わせ
# 開発環境の完全リセット
docker compose down --remove-orphans
docker compose up -d --build --force-recreate --remove-orphans
# CI/CD用の実行コマンド
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ci.yml up \\
--build --abort-on-container-exit --remove-orphans
# 特定サービスのトラブルシューティング
docker compose up --no-deps --force-recreate --build web
# 本番環境デプロイ時の慎重な起動
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d \\
--quiet-pull --remove-orphans
エイリアス設定による効率化
よく使用するオプションの組み合わせは、シェルのエイリアスに登録することで作業効率を向上させることができます:
.bashrc または .zshrc に追加:
# 開発用
alias dcu='docker compose up -d'
alias dcub='docker compose up -d --build'
alias dcur='docker compose up -d --build --force-recreate --remove-orphans'
# 本番用
alias dcup='docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --quiet-pull --remove-orphans'
# デバッグ用
alias dcl='docker compose logs -f'
alias dcs='docker compose ps'
これらのdocker compose up オプションテクニックを活用することで、様々な開発シナリオに柔軟に対応でき、チーム開発での効率性も大幅に向上します。次のセクションでは、トラブルシューティングと環境別の最適化について詳しく解説していきます。
トラブルシューティングと環境別の最適化ノウハウ
docker compose upコマンドを実行する際に発生する様々な問題の解決方法と、開発環境・本番環境・CI/CDそれぞれに最適化されたオプションの使い分けについて詳しく解説します。実際の開発現場で遭遇しやすいトラブルと、その効率的な対処法をマスターしましょう。
upが終わらない/ハング時の原因と解決法
よくある原因と対処法の体系的アプローチ
docker compose upが終わらない、または途中でハングしてしまう問題は開発現場でよく発生します。以下の順序で原因を特定し、解決していきましょう。
1. ログの確認による問題特定
基本的な確認コマンド:
# 現在のコンテナ状態を確認
docker compose ps
# 全サービスのログを確認
docker compose logs
# 特定のサービスのログを確認
docker compose logs web
# リアルタイムでログを監視
docker compose logs -f --tail=50
# タイムスタンプ付きでログを確認
docker compose logs -t
ログ確認の実践例:
# エラーが発生しているサービスを特定
docker compose ps
# 出力例:
# NAME COMMAND SERVICE STATUS PORTS
# myapp-web-1 "npm start" web Exited (1)
# myapp-db-1 "docker-entrypoint…" db Up 2 minutes 5432/tcp
# 異常終了したサービスのログを詳細確認
docker compose logs web
# エラー内容を基に対処方針を決定
2. ポート競合の確認と解決
ポート使用状況の確認:
# 使用中のポートを確認(Linux/Mac)
lsof -i :3000
netstat -tulpn | grep :3000
# Windows の場合
netstat -ano | findstr :3000
競合解決のコード例:
元のdocker-compose.yml(問題のある設定):
services:
web:
build: .
ports:
- "3000:3000" # 既に使用中のポート
修正後(ポート番号を変更):
services:
web:
build: .
ports:
- "3001:3000" # 空いているポートに変更
または環境変数を活用:
services:
web:
build: .
ports:
- "${WEB_PORT:-3000}:3000"
# 環境変数でポートを指定して起動
WEB_PORT=3001 docker compose up -d
3. 依存関係の問題と解決
depends_onの正しい設定例:
version: '3.8'
services:
web:
build: .
depends_on:
db:
condition: service_healthy # ヘルスチェック完了を待機
environment:
- DATABASE_URL=postgresql://user:password@db:5432/myapp
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_USER=user
- POSTGRES_PASSWORD=password
- POSTGRES_DB=myapp
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U user -d myapp"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 5
依存関係のトラブルシューティングコマンド:
# 依存関係を無視して個別に起動し、問題を特定
docker compose up -d --no-deps db
docker compose logs db
# データベース接続確認
docker compose exec db pg_isready -U user -d myapp
# 依存関係を含めて段階的に起動
docker compose up -d db
sleep 10
docker compose up -d web
4. メモリ・リソース不足の対処
リソース使用状況の確認:
# Docker リソース使用状況
docker stats
# システムリソース確認
free -h # メモリ使用量
df -h # ディスク使用量
docker-compose.ymlでリソース制限を設定:
services:
web:
build: .
deploy:
resources:
limits:
memory: 512M
cpus: '0.5'
reservations:
memory: 256M
cpus: '0.25'
db:
image: postgres:13
deploy:
resources:
limits:
memory: 1G
cpus: '1.0'
-remove-orphans・-abort-on-container-exit等トラブル対応用オプション
-remove-orphansによるクリーンアップ戦略
孤立コンテナが引き起こす問題:
# 現在のプロジェクトに関連する全コンテナを確認
docker compose ps -a
# 孤立コンテナも含めた全コンテナを確認
docker ps -a --filter "label=com.docker.compose.project=myapp"
段階的クリーンアップの実践例:
# ステップ1: 現在のサービスを停止
docker compose down
# ステップ2: 孤立コンテナも含めて完全削除
docker compose down --remove-orphans --volumes
# ステップ3: クリーンな状態で再起動
docker compose up -d --build --remove-orphans
# ステップ4: 起動確認
docker compose ps
docker compose logs --tail=20
-abort-on-container-exitを活用したテスト・デバッグ
テスト環境での活用例:
docker-compose.test.yml:
version: '3.8'
services:
test-runner:
build:
context: .
dockerfile: Dockerfile.test
command: npm run test:integration
depends_on:
- db
- redis
environment:
- NODE_ENV=test
- DATABASE_URL=postgresql://test:test@db:5432/testdb
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_USER=test
- POSTGRES_PASSWORD=test
- POSTGRES_DB=testdb
tmpfs:
- /var/lib/postgresql/data # テスト用の一時的なデータ
redis:
image: redis:7-alpine
実践的なテスト実行コマンド:
# テスト実行(完了後に全サービス停止)
docker compose -f docker-compose.test.yml up --build --abort-on-container-exit
# テスト結果の確認
echo $? # 終了コードを確認(0が成功)
# 失敗時のデバッグ情報取得
docker compose -f docker-compose.test.yml up --build --abort-on-container-exit || {
echo "テストが失敗しました。ログを確認中..."
docker compose -f docker-compose.test.yml logs
}
効果的なトラブルシューティングワークフロー
問題発生時の標準的な対処手順:
#!/bin/bash
# トラブルシューティング用スクリプト
echo "=== Docker Compose トラブルシューティング開始 ==="
# 1. 現在の状態確認
echo "1. 現在のコンテナ状態:"
docker compose ps
# 2. ログの確認
echo "2. 最新のログ:"
docker compose logs --tail=50
# 3. システムリソース確認
echo "3. システムリソース:"
docker stats --no-stream
# 4. クリーンな再起動を試行
echo "4. クリーンな再起動を実行中..."
docker compose down --remove-orphans
docker compose up -d --build --force-recreate --remove-orphans
# 5. 起動結果確認
sleep 10
echo "5. 再起動後の状態:"
docker compose ps
# 6. ヘルスチェック
echo "6. サービスヘルスチェック:"
for service in $(docker compose config --services); do
echo "Checking $service..."
docker compose exec -T $service echo "OK" 2>/dev/null || echo "$service: 接続できません"
done
echo "=== トラブルシューティング完了 ==="
開発・本番環境/CIでのベストプラクティス・運用ルール構築法
開発環境のベストプラクティス
開発環境用の推奨設定:
docker-compose.dev.yml:
version: '3.8'
services:
web:
build:
context: .
target: development # マルチステージビルドの開発ターゲット
volumes:
- .:/app
- /app/node_modules # node_modulesを除外
environment:
- NODE_ENV=development
- DEBUG=*
- CHOKIDAR_USEPOLLING=true # ファイル監視の設定
command: npm run dev
db:
ports:
- "5432:5432" # 外部ツールでの接続用
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=dev_password
volumes:
- postgres_data_dev:/var/lib/postgresql/data
volumes:
postgres_data_dev:
開発環境での推奨コマンド:
# 日常的な開発作業用
alias dev-up='docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build'
alias dev-logs='docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml logs -f'
alias dev-down='docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml down'
# 開発環境のリセット(データを保持)
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml down
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build --force-recreate
# 完全リセット(データも削除)
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml down --volumes
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build
本番環境のベストプラクティス
本番環境用の推奨設定:
docker-compose.prod.yml:
version: '3.8'
services:
web:
build:
context: .
target: production
environment:
- NODE_ENV=production
deploy:
replicas: 3
resources:
limits:
memory: 512M
cpus: '0.5'
restart_policy:
condition: on-failure
max_attempts: 3
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: "10m"
max-file: "3"
db:
environment:
- POSTGRES_PASSWORD_FILE=/run/secrets/db_password
secrets:
- db_password
volumes:
- postgres_data_prod:/var/lib/postgresql/data
deploy:
resources:
limits:
memory: 2G
cpus: '1.0'
secrets:
db_password:
external: true
volumes:
postgres_data_prod:
external: true
本番環境での推奨デプロイフロー:
#!/bin/bash
# 本番環境デプロイスクリプト
set -e # エラー時に停止
echo "=== 本番環境デプロイ開始 ==="
# 1. イメージの事前ビルド
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml build
# 2. ヘルスチェック付きデプロイ
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d \\
--remove-orphans --quiet-pull
# 3. デプロイ確認
sleep 30
if docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml ps | grep -q "unhealthy\\|exited"; then
echo "デプロイに失敗しました。ロールバックします..."
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml logs
exit 1
fi
echo "=== デプロイ完了 ==="
CI/CD環境のベストプラクティス
GitHubActions用の設定例:
.github/workflows/ci.yml:
name: CI/CD Pipeline
on: [push, pull_request]
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: Run tests
run: |
# テスト用の環境変数設定
export DATABASE_URL=postgresql://test:test@localhost:5432/testdb
# テスト実行(失敗時は自動停止)
docker compose -f docker-compose.test.yml up \\
--build --abort-on-container-exit --remove-orphans
# 終了コードを保存
TEST_EXIT_CODE=$?
# ログの出力(デバッグ用)
docker compose -f docker-compose.test.yml logs
# クリーンアップ
docker compose -f docker-compose.test.yml down --remove-orphans --volumes
# テスト結果で判定
exit $TEST_EXIT_CODE
CI/CD用のコマンド最適化:
# CI環境での高速化設定
export COMPOSE_DOCKER_CLI_BUILD=1
export DOCKER_BUILDKIT=1
# テスト実行(並列化とキャッシュ活用)
docker compose -f docker-compose.test.yml up \\
--build --parallel --abort-on-container-exit \\
--remove-orphans --quiet-pull
# 本番デプロイ(ダウンタイム最小化)
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d \\
--no-deps --remove-orphans web # webサービスのみ更新
チームでの運用ルール構築
Makefileを活用した標準化:
# Makefile
.PHONY: dev-up dev-down dev-logs test deploy
# 開発環境
dev-up:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build
dev-down:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml down
dev-logs:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml logs -f
dev-reset:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml down --volumes
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build
# テスト
test:
docker compose -f docker-compose.test.yml up --build --abort-on-container-exit --remove-orphans
docker compose -f docker-compose.test.yml down --remove-orphans --volumes
# 本番デプロイ
deploy:
./scripts/deploy-prod.sh
使用方法:
# 開発環境起動
make dev-up
# テスト実行
make test
# 本番デプロイ
make deploy
これらのトラブルシューティング手法と環境別最適化を実践することで、docker compose up オプションを使った効率的で安定した開発・運用環境を構築できます。次のセクションでは、よくある質問について詳しく解説していきます。
よくある質問(FAQ)
-
docker compose upとdocker compose buildの違いは? -
docker compose buildはイメージのビルドのみを行います。コンテナは作成も起動もされません。一方、docker compose upはイメージのビルド(--buildオプションがある場合)、コンテナの作成、そして起動までの一連の流れを自動的に行ってくれます。
-
up時にDockerfileの変更が反映されないのはなぜ? -
docker compose upは、Dockerfileの変更を自動的に検知しません。変更を反映させるには、--buildオプションを付けてコマンドを実行する必要があります。docker compose upは、Dockerfileの変更を自動的に検知しません。変更を反映させるには、--buildオプションを付けてコマンドを実行する必要があります。
-
--force-recreateと--renew-anon-volumesの違いは? -
--force-recreateはコンテナ自体を再作成します。これに対し、--renew-anon-volumesは匿名ボリュームを再作成し、既存のボリュームは無視して、新しいボリュームを紐づけます。
まとめ
この記事では、docker compose up オプションの基本から実践的な活用法まで幅広くご紹介しました。Docker Composeの基本知識はあっても、オプションを十分に活用できていなかった方も多いのではないでしょうか。
まず押さえておきたいのは、必須オプション5選です。-dでバックグラウンド実行、--buildでイメージ再ビルド、--force-recreateでコンテナ強制再作成、--no-depsで依存関係無視、そしてサービス名指定での部分起動。これらを使いこなすだけで、日々の開発作業が格段にスムーズになります。
さらに実践的なテクニックとして、-fオプションによる複数ファイル管理は特に重要です。開発環境と本番環境で設定を分けることで、環境固有の問題を大幅に減らせます。docker-compose.override.ymlの自動読み込み機能も併せて活用すれば、個人の開発環境も柔軟にカスタマイズできるでしょう。
トラブルシューティングについても体系的にアプローチすることが大切です。docker compose upがハングした時は、まずログ確認から始めて、ポート競合、依存関係、リソース不足の順で原因を特定していきます。--remove-orphansで不要なコンテナを削除し、--abort-on-container-exitでテスト環境を効率化するなど、状況に応じた使い分けがポイントです。
環境別の最適化では、開発環境ではホットリロードとデバッグを重視し、本番環境ではセキュリティとパフォーマンスを最優先にします。CI/CD環境では並列化とキャッシュ活用で処理時間を短縮することが重要です。
これらのdocker compose up オプションを適切に使い分けることで、開発効率は確実に向上し、トラブル発生時の対応もスピーディーになります。コンテナ環境での開発が当たり前となった今、これらのテクニックは必須スキルと言えるでしょう。
今日から早速、普段のコマンドにオプションを追加して、Docker Composeを使いこなしていきましょう。最初は基本的な-dや--buildから始めて、徐々に複数ファイル管理やトラブルシューティング手法も取り入れてみてください。きっと、これまで以上に快適な開発環境を構築できるはずです。